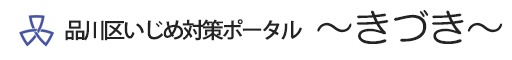更新日 2024年07月22日
いじめが、被害者の心身に大きな影響を与えていると推測されたり、少なくない金額の金銭的な問題が起きていたり、不登校に影響していると推測できたりする場合は、「いじめ防止対策推進法」の「重大事態」としての対応が必要になります。
同法の「第五章 重大事態への対処」の第二十八条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)では、「学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。」
としています。
いじめ事例の解決に向けての流れの例については別のところで紹介していますが、「重大事態」に相当すると考えられる深刻ないじめに対しては、同法に沿って、調査委員会の設置など、区を含めた学校外部と連携しての対応が必要となります。
「重大事態」に該当する可能性があるのに、「速やかに」対処しなかった場合は、大きな問題となります。そのためにも早い段階で情報を教職員で共有し、複数の視点で事態について検討することが重要です。