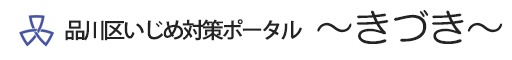更新日 2024年07月22日
「いじめ防止対策推進法」では基本理念として、第三条で、次の三つを挙げています。
- いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
- いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
- いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
いじめ防止等の取り組みは、「学校の内外を問わずいじめが行われなくなるように」行う必要があり、その対策は教職員だけでなく、「国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他関係者」が連携してあたることが理念とされています。
そして、学校や教職員の責務について、次のように掲げています(第八条)。
「学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」
つまり、学校、そして教職員は、いじめがあると「思われる」段階で、「適切かつ迅速にこれに対処する責務」があります。いじめの事実を確認して、悪意のあるいじめがあったと認定してから動くのではなく、本人の苦痛の訴えなど、いじめがあると疑われる段階から、対応をすることが必要です。そして、いじめへの対処は、教職員がひとりで抱え込まず、学校として組織的に取り組むことが求められています。保護者や地域住民等とも連携しながら、組織的に取り組む必要があること、そのためには、校内での対応の流れや組織について校内で共有しておくことが重要です。
熱心な教職員ほど、「自分が解決しなくては…」「担任として、ほかに迷惑はかけられない…」とひとりで抱え込みがちです。しかし、いじめは組織で対応すべき問題です。必ず周囲に報告すること、そのためには、普段からお互いに相談できる組織であることが大事です。