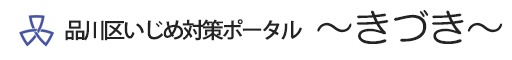更新日 2024年01月04日

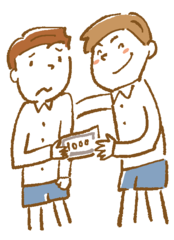
例えば、次のようなことがいじめになります。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
- 仲間はずれ、集団による無視をされる。
- 嫌なあだ名で呼ばれる。
- 軽くぶつけられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、けられたりする。
- ひどくぶたれたり、叩かれたり、蹴られたりする。
- 金品をたかられる。
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
- パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。
文部科学省「いじめの現状について~いじめの態様別状況」を参考に作成
<参考>
「いじめ防止対策推進法」では、いじめを次のように定義しています。
「【定義挿入】児童等に対して、当該児童等が在籍する 学校に在籍している等当該児童等と一 定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。) であって、当該行為の対象と なった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
この定義の特徴は、いじめを受けた側の心身の痛みを重視している点です。
何か行為があった時に、それを受けた側が、苦痛を感じるものであれば、それはいじめとして、周囲も対応を講じることが必要とされています。
ネット上のいじめも増えています

- グループトークで「○○ウザい」などを悪口を書かれている。
- 別グループトークを作られて、仲間外れにされる。
- 自分の名前で「恋人募集中」などのウソの投稿をさせられる。
- 更衣室などの性的な画像などを投稿される。
- SNSでウソを書かれる。
- プライバシーに関わることや私的な行動を、勝手にSNSの書き込みで広められる。
- なりすましのアカウントを作られ、ウソの情報を書かれたり、メールを送られたりする。
- 自分の名前を使われて、「〇〇先生は✖✖と▽▽している」などのウソを書かれる。
ネットのいじめの特徴
- 不特定多数の者から、絶え間なく誹謗・中傷が行われ、被害が短期間で極めて深刻なものとなる。
- インターネットの持つ匿名性から、安易に誹謗・中傷の書き込みが行われるため、子どもが簡単に被害者にも加害者にもなる。
- インターネット上に掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易にできることから、誹謗・中傷の対象として悪用されやすい。
- インターネット上に一度流出した個人情報は、回収することが困難となるとともに、不特定多数の他者からアクセスされる危険性がある。
- 保護者や教師などの身近な大人が、子どもの携帯電話等の利用の状況を把握することが難しい。また、子どもの利用している掲示板などを詳細に確認することが困難なため、「ネット上のいじめ」の実態の把握が難しい。
- 大人の目に触れにくいことから、子どもが自分の判断で不適切な投稿をすると、周囲の子も止められずに、短期間に広まってしまう。
資料:文部科学省「『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集(学校・教職員向け)」

いじめられている子どもは、顔の見えない不特定多数から攻撃されていると感じるため、対象の明確ではない不安を抱いてしまいます。
いじめている子は、重大さを認識しづらく、犯罪などにつながりやすい傾向があります。
「いじめ」は、執拗な嫌がらせや暴力だけではありません。
加害者である子どもに悪気はなく、軽い気持ちでの「いじり」や「ちょっかい」、「冗談」と思っていた行為であったとしても、被害者である受けた子どもが苦痛を感じていたり、いやな思いをしていれば、それは「いじめ」です。
学校では、さまざまな子どもたちが集団で生活を送るなかで、「いじめ」はいつでも起こりうること、また、どの子どももいじめの被害者にも加害者にもなってしまうことが可能性としてあります。
そのため、保護者だけでなく、子どもたちの周囲の大人が、次世代を担う子どもたちを見守り、安心して健やかに成長できる環境を築いていくことが大切です。
「いじめ」を深刻なものにさせないためには、早期に周囲の大人たちが協力することが大事です